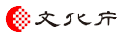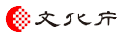|
名称 |
: |
御正体 |
|
ふりがな | : |
みしょうたい |
|
解説表示▶
|
|
員数 |
: |
5面 |
|
種別 |
: |
工芸品 |
|
国 |
: |
日本 |
|
時代 |
: |
鎌倉 |
|
年代 |
: |
|
|
西暦 |
: |
|
|
作者 |
: |
|
|
寸法・重量 |
: |
①盤径34.8 像高24.7
②盤径22.2 像高11.2
③盤径31.6 像高18.3
④盤径30.4 像高17.0
⑤盤径21.5 像高11.0 (㎝) |
|
品質・形状 |
: |
①円形の周縁に覆輪を施し、中央に両腕を別鋳し、肩で装着した金剛界大日如来の半面像を据える。光背は頭光と身光の二重輪光で、上部左右二ヶ所づつ翼状板金の火焔を打つ。釣鐶座は花形で二重菊座のある切子鐶台をつける。一群の中で最も時代が古く、鎌倉期の作と考えられる。
②円形の周縁に覆輪を施し、中央に金剛界大日如来坐像を据える。像に火焔付き二重輪光を付けるが、火焔には朱漆を塗る。仏体の台座には細かい線刻を加えている。盤裏に朱漆銘がある。
③円形の周縁に幅広の飾覆輪を施し、中央には金剛界大日如来像を鋲止めする。唐草文透彫の舟形光背を負い、頭上には天蓋、像の左右に花瓶を鋲止めする。鍍銀の像、幅広の飾覆輪などはあまり類を見ない。
④円形の周縁に三点、二点の笠鋲を打った覆輪を施し、中央に胎蔵界大日如来坐像を据える。像は丸ものに近い半面造であり、両手は別鋳で、肩に蟻ほぞで落とし込む。頭髪、眉目、口唇などに彩色を施す。台座は金銅板の蓮弁を四段に葺き連ね、蓮座には蕊を刻む。釣鐶座は鼻形で魚々子地に花を線刻する。切子鐶台付。
⑤円形の終演に覆輪を施し、周縁に金剛界大日如来坐像を据える。像は蓮華座共に一鋳で、唐草文透彫の舟形光背を負う。天蓋の残片が残り、像の左右には花瓶を鋲止めする。盤裏の檜板に墨書銘がある。 |
|
ト書 |
: |
うち一面に弘安元年卯月廿一日の朱漆銘、一面に弘安九年十二月廿二日の墨書銘がある |
|
画賛・奥書・銘文等 |
: |
②「敬奉新造/御正軆一面/右為二世之(悉)地/成就之也/(弘)安元年戌/虎(卯)月廿一日/大勧進金剛佛子理有覚/大施主平氏女」 (悉=米の下に心、弘=方ム、卯=夕卩)
⑤「神明御正躰一面/弘安九年大才/丙戌十二月廿二日/願主比丘尼妙法」 |
|
伝来・その他参考となるべき事項 |
: |
|
|
指定番号(登録番号) |
: |
02068 |
|
枝番 |
: |
00 |
|
国宝・重文区分 |
: |
重要文化財 |
|
重文指定年月日 |
: |
1961.02.17(昭和36.02.17) |
|
国宝指定年月日 |
: |
|
|
追加年月日 |
: |
|
|
所在都道府県 |
: |
長野県 |
|
所在地 |
: |
|
|
保管施設の名称 |
: |
|
|
所有者名 |
: |
仁科神明宮 |
|
管理団体・管理責任者名 |
: |
|