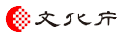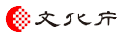|
名称 |
: |
会津只見の生産用具と仕事着コレクション |
|
ふりがな | : |
あいづただみのせいさんようぐとしごとぎこれくしょん |
会津只見の生産用具と仕事着コレクション(山樵用具)
写真一覧▶
地図表示▶
解説表示▶
|
|
員数 |
: |
2,333点 |
|
種別 |
: |
生産、生業に用いられるもの |
|
年代 |
: |
|
|
その他参考となるべき事項 |
: |
内訳:生産用具1,917点 仕事着416点 |
|
指定番号 |
: |
00214 |
|
指定年月日 |
: |
2003.02.20(平成15.02.20) |
|
追加年月日 |
: |
|
|
指定基準1 |
: |
(二)生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 |
|
指定基準2 |
: |
(一)衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 |
|
指定基準3 |
: |
(三)地域的特色を示すもの |
|
所在都道府県 |
: |
福島県 |
|
所在地 |
: |
南会津郡只見町大字大倉字窪田30番地 |
|
保管施設の名称 |
: |
ただみ・モノとくらしのミュージアム |
|
所有者名 |
: |
只見町 |
|
管理団体・管理責任者名 |
: |
|
|
会津只見の生産用具と仕事着コレクション(山樵用具)
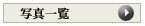
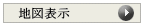
|